歴史の扉へようこそ。旅人です!
今回訪ねるお寺は京都・三十三間堂付近に建つお寺、養源院です!
こちらのお寺、実は、天井に戦国武将たちの血がべったりついた「血天井」で有名なお寺なんです!
お寺の前に「血天井」と書かれた看板を見て、「えっ、どういうこと!?怖い!」と思い、ついつい中へ足を運んでしまいました(^^;)
さて、この養源院はいったいどんなお寺なんでしょうか?
今回の記事では、下記について解説します。
- 養源院の歴史
- 戦国武将たちの血で染まった「血天井」とは?
- いただいてきた御朱印紹介
養源院の歴史
上記Tweetのとおり、養源院は浅井長政の娘であり、豊臣秀吉の側室でもある淀殿が父の菩提を弔うために建立したお寺です。その後、淀殿の妹で、2代将軍徳川秀忠の正室お江により再建されました。
大坂の陣で徳川と豊臣は戦うため、全国の大半の寺社では徳川と豊臣の位牌がならぶことはありません。
しかし、養源院では、創建の経緯から、浅井・豊臣・徳川の位牌が並ぶ、全国でもかなり珍しいお寺になっています。
俵屋宗達の杉戸絵など養源院境内
境内写真

門からまっすぐ伸びる参道。

本堂には徳川家の家紋・葵御紋が大きく描かれている。
俵屋宗達の杉戸絵

こちらは養源院でいただいたポストカードを撮影したもの。(※養源院にある本物は撮影禁止でした!)
漫画チックなタッチの中にも、迫力があって、とても見ごたえのある絵です。
血天井
住職によるガイド
本堂では、住職の方が血天井の解説をしてくれます。晴れた日には日光が入り、血の跡が良く見えます。なんと、武将の体の形にそって、血が残っているのです!
「ここが頭で、ここが刀、ここが肩で、ここが足。」
みたいな感じで、長い竿を使って解説してくれます。
血天井は誰の血?
では、この血は一体誰の血なんでしょうか?
じつは関ケ原の戦いの前哨戦で、伏見城の戦いという戦がありました。
この戦で、徳川方と石田方がぶつかり、伏見城にいた徳川方の鳥居元忠軍は敗北することとなります。
その際、負けを悟った鳥居軍は伏見城で自決。血でぬれた床板をそのまま天井にはめることで、鳥居軍の霊を弔ったのでした。
なぜ養源院に?
なぜ養源院に血天井をはめる必要があったのでしょうか。
養源院の歴史の項で書いたように、養源院は豊臣方の淀殿が建てたお寺です。いくら妹の江が姉のためにとはいえ、豊臣家が建てた寺を再建することに幕府の許可を得ることがかなり難しかったのです。
そこで、「伏見城の戦いでの徳川方の武将を弔うため」という理由が必要だったのです。
敵味方に分かれたとはいえ、家族の思いを大事にしたいというお江の願いが伝わりますね。
御朱印
御朱印
・通常の御朱印

・麒麟の御朱印

限定御朱印帳

木製で、杉戸絵が彫られた御朱印帳も販売していました!気になる方はぜひ!
「そもそも御朱印って何?」という方はこちらの記事もどうぞ。
アクセス
J R:京都駅より市バス100・206・208系統「博物館三十三間堂前」バス停下車。徒歩3分。
京阪電車:七条駅より徒歩約10分。
付近の三十三間堂や法住寺も要チェック!
まだ読んでいない方は下記の記事もどうぞ。
まとめ
- 養源院は、淀殿・お江の願いが込められた浅井・豊臣・徳川ゆかりのお寺
- 「血天井」は武将たちを弔うためのものだった!
- 俵屋宗達の杉戸絵は必見!間近で見られる!
最後まで読んでいただき、ありがとうございます!
コロナでなかなか寺社巡りに出かけることもできませんが、このブログを読んでいただき、
「Stay Homeで寺社参拝」
した気分になっていただければ幸いです。是非、他の記事も覗いていってください!
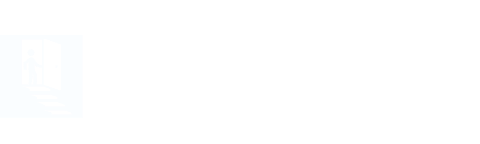





コメント